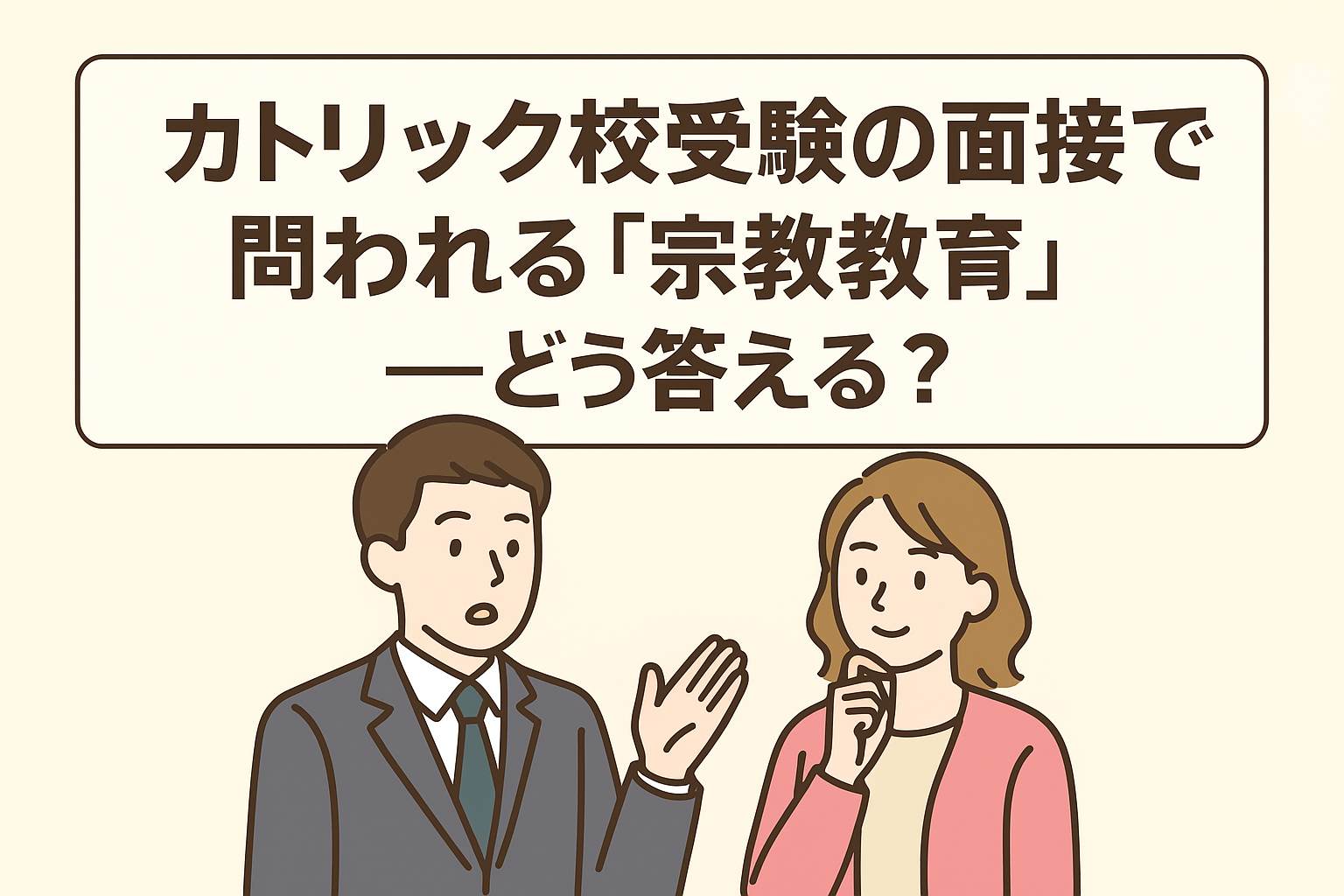「人間は一人では生きられない」
この言葉は、宗教教育の意義を考える出発点になるかもしれません。
医療の発達により、人生100年時代を迎えました。病気は治せるようになりました。しかし――心の豊かさはどうでしょうか。孤独、迷い、不安は、医療だけでは解決できません。
宗教の本質は「ご利益」ではありません。
人に願いがあるように、神にも願いがある。そこに気づくことが、祈りの意味につながります。たとえば、朝晩の感謝の祈り。これは単なる儀式ではなく、自分自身を整える「心の習慣」になり得るのです。
では、宗教教育は何を生徒にもたらすのでしょうか?
21世紀において宗教の役割は、孤独を救うことかもしれません。しかし、青年期の少年少女にとってはどうでしょう?
「全知全能の神が、戦争や災害を止められないのはなぜか?」
こうした疑問を投げかけ、考えさせること。それは答えの出ない問いに向かう姿勢を育む営みです。受験や学力だけでは測れない、人間としての深さを育てる教育と言えるでしょう。
カトリック校受験の面接で問われる「宗教教育」――どう答える?
カトリック系の学校では、親御さんへの面接でよく聞かれる質問があります。
それが――
「宗教教育についてどうお考えですか?」 です。
信者でなくても心配はいりません。大切なのは、学校の教育方針を理解し、お子さんの成長と結びつけて語れることです。
1.宗教教育は「人の幸せを願う心」を育てる
どの宗教でも共通しているのは「人の幸せを願う心」です。
「宗教教育を通して、自分や他者を大切にする心を学んでほしいと思います」
といった答え方は好印象です。
2.祈りや感謝の習慣は、心を整える
「朝夕に祈る」「感謝の気持ちを持つ」といった宗教教育の習慣は、子どもの心を落ち着かせる役割があります。
親としては、
「受験勉強だけでなく、感謝や祈りの習慣を通して心も育ててほしい」
と答えるとよいでしょう。
3.答えのない問いに向き合う力を養う
「なぜ戦争や災害があるのか?」といった宗教的テーマには、正解がありません。
しかし、そうした問いに向き合う姿勢は、学力を超えた“考える力”を育てます。
「子どもが、勉強だけでなく、人として深く考える力を養ってくれる教育に魅力を感じます」
という答え方も評価されます。