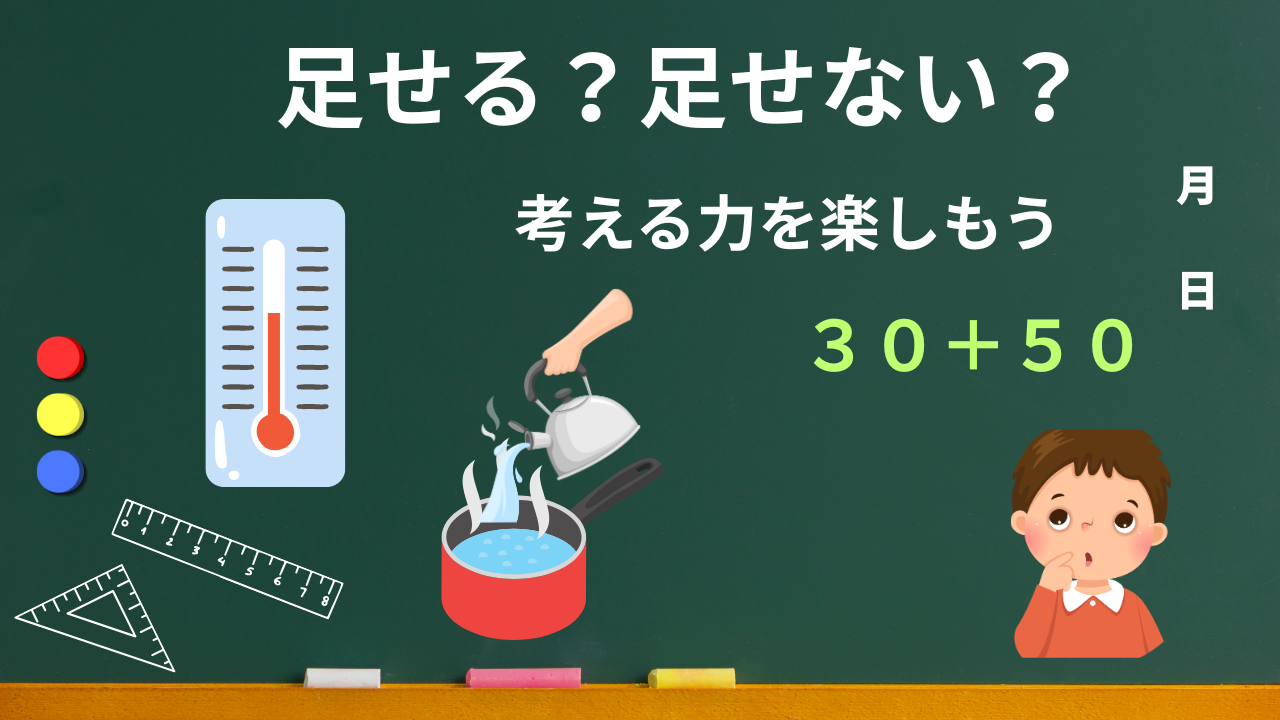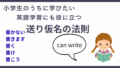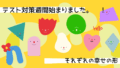足せる?足せない?掛け算になる?ならない?
〜考えることを楽しむ力が未来をつくる〜
「30度のお湯と50度のお湯を合わせると何度になるでしょう?」
パッと「30+50=80!」と答えたくなりますが、実はそうはいきません。
温度は混ぜれば性質が変わるので、そのまま足すことはできないのです。
ところが、こんな問題もあります。
「昨日の気温は30度でした。今日の気温は昨日より5度高いです。さて今日の気温は?」
この場合は 30+5=35。足すことができます。
ここで大事なのは、「あわせる」だから「足す」のではなく、何を表しているのかを考えることです。
掛け算の例
掛け算は「同じものがいくつ分あるか」を考えるときに使います。
- 1袋に30個のみかんが入っていて、袋が50袋あるとき → 30 × 50
- 映画館の1列に30席あって、全部で50列あるとき → 30 × 50
このように「同じものが並ぶ」イメージがあるときは掛け算です。
掛け算にならない例
例1:確率の場合
サイコロを振って「30%の確率で当たり」と「50%の確率で当たり」があったとしても、
両方を同時に考えるとき 30%×50%=15% にはなりません。
なぜなら確率は事象の関係(独立か従属か、重なりがあるか)によって計算式が変わるからです。
例2:成長率や割引率
100円の商品に「30%割引」をしてから「50%割引」をするとき、
計算は
- 100円 → 70円(30%引き)
- 70円 → 35円(さらに50%引き)
最終価格は 35円。
このとき「30%×50%=15%」ではなく「最終的に65%引き」になります。
例3:デシベル(音の大きさ)
音の大きさは「デシベル(dB)」で表します。
30dBと50dBを足して「80dB」にはならず、また掛け算して「1500」になるわけでもありません。
デシベルは対数の単位なので、強さの合成は数式が全く別になります。
つまり「30×50」も場面によってはそのまま掛け算の意味にならないわけです。
大事なのは「この場面は掛け算?足し算?」ではなくそれとも別の考え方をと
自分で考えることです。
ドリルだけでは育たない力
小さいころから“答えのあるドリル”ばかり解いていると、こうした根本的な「なぜ?」に弱くなります。
式を立てる前に考える力こそが、これからの学びで一番大事な土台です。
だからこそ、家庭での「ちょっとした会話」が宝物になります。
「これはなぜ足せる?」「掛け算になるかなぁ?」「混ぜたらどうなる?」と、身近なことを親子で話す時間が、机の上の勉強以上に力を伸ばします。
聖霊VAPや中高一貫、名大付属が入試が求めているもの
聖霊VAP入試や中高一貫、名大付属では、まさにこの「自分で考えることを楽しむ姿勢」を大切にしています。
正解を素早く出すよりも、どう考えたのか、なぜそう思ったのかを大切にできる子が輝きます。
🌱 まとめ
- 足せるときと足せないときがある
- 掛け算は「同じものがいくつ分あるか」
- でも掛け算にならない場面もある
- ドリルより大切なのは「考えることを楽しむ習慣」
- 聖霊VAP入試はこの力を求めている
「なるほど、うちの子にもこういう会話をしてあげたい!」と感じられた方は、ぜひ一度ご相談ください。
家庭での会話が、お子さんの未来を変える一歩になるはずです。