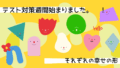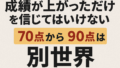中学入試で伸び悩む子の共通点とは?
小さいうちから大切にしたい「挑戦の経験」
小学校低学年のうちは、算数や漢字のテストで満点を取る子が少なくありません。
親御さんとしては「このままいけば中学入試もうまくいくのでは」と期待する気持ちも自然でしょう。
しかし実は、その「簡単に結果が出せる」という状況が、後の伸び悩みにつながることがあるのです。
「努力なしの成果」は心に残らない
人は不思議なもので、苦労せずにできてしまったことにはあまり価値を感じません。
テストで満点を取ったとしても、それが努力の結果でなければ本人の記憶にも自信にも残りにくいのです。
また、「できることだけを繰り返す」勉強も要注意。計算問題をスラスラ解けることに安心していると、本当に大切な「考える力」が育ちません。
伸びる子に共通する姿勢
学びの本質は「少し背伸びをして挑戦すること」にあります。
例えば、習っていない漢字に出会ったときに、
「まだ習っていないから」とひらがなで済ませてしまう子は要注意です。
やがて難しい問題に出会ったとき、「無理」とあきらめてしまう姿勢につながりやすいからです。
逆に、「知らないけど調べてみよう」「推測して書いてみよう」と取り組む経験を積んだ子は、困難に直面しても粘り強く挑戦できるようになります。
勉強以外でも「挑戦の経験」を
大切なのは、小さいうちから「努力と結果をセットで体験する」こと。
これは勉強に限らず、スポーツや遊びの中でも十分に培えます。
- 鉄棒で逆上がりに挑戦する
- 苦手な積み木やパズルに時間をかけて取り組む
- 難しいゲームのステージを工夫してクリアする
こうした体験を通して「工夫して挑戦し、失敗しながらできるようになった」という成功体験を積むことが、後の学びや挑戦の土台になります。
まとめ
子どもが社会に出たときに必要とされるのは、ただの「賢さ」ではありません。
知識や能力を活かし、挑戦し続ける力です。
その力は、幼いころの「ちょっと苦労したけど、やり遂げられた」という経験の積み重ねから育ちます。
だからこそ、小学校低学年の今こそ――
「努力してできるようになる喜び」を味わわせることが何より大切なのです。